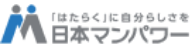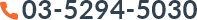キャリアコンサルタントLibrary
人の力になりたいという気持ちが原動力!それが社会の役に立つのがキャリアコンサルタント資格です!!
その他
ジョブ・カードとは?part2 企業・個人の活用メリットを徹底解説!

厚生労働省が推奨する「ジョブ・カード」を企業、個人と対象別の活用方法について解説します。
企業が導入するメリットやデメリット、自社の人材育成や個人のキャリア形成にお役立てください。
ジョブ・カードの基本的な内容、具体的な作成手順、さらに活用できる助成金制度については以下よりご確認ください。
関連記事: ジョブ・カードとは?part1 基本情報について徹底解説!
【企業向け】ジョブ・カード導入のメリット
企業がジョブ・カード制度を導入し、積極的に活用することには、多くのメリットが期待できます。従業員のキャリア自律を促し、組織全体の活性化につながるだけでなく、具体的な経営課題の解決にも貢献する可能性があります。従業員のキャリア自律促進
ジョブ・カードの作成を通じて、従業員は自身のキャリアを客観的に見つめ直し、将来の目標や習得すべきスキルを具体的に考える機会を得ます。これにより、他人任せではない、主体的なキャリア形成意識(キャリア自律)が育まれます。 キャリア自律した従業員は、自己成長意欲が高く、変化への対応力も向上する傾向があります。これは、予測困難な現代のビジネス環境において、企業が持続的に成長していくための重要な原動力となります。企業がジョブ・カードを活用して キャリアコンサルティング の機会などを提供することで、この動きをさらに後押しできます。計画的な人材育成の実現
ジョブ・カードは、従業員一人ひとりのスキルや経験、キャリアプランを「見える化」します。企業はこれらの情報を集約・分析することで、個々の従業員に適した研修プログラムやOJTを計画的に実施できるようになります。 また、従業員の希望や適性を踏まえた配置転換や能力開発が可能となり、人材育成のミスマッチを防ぎ、効果を最大化することにもつながります。結果として、組織全体のスキルレベル向上と、将来のリーダー候補の育成にも貢献します。コミュニケーションの活性化とエンゲージメント向上
ジョブ・カードを活用した上司と部下の面談は、単なる業務報告の場ではなく、部下のキャリアプランや悩みについて深く話し合う貴重な機会となります。これにより、相互理解が深まり、信頼関係が構築されやすくなります。 部下は、会社が自分のキャリアに関心を持ってくれていると感じることで、組織への帰属意識や貢献意欲(エンゲージメント)が高まることが期待できます。エンゲージメントの高い従業員は、生産性の向上や離職率の低下にもつながるため、企業にとって大きなメリットとなります。
関連リンク:
コラムVol.2『なぜセルフ・キャリアドックが必要なのか』 | キャリアコンサルタントLibrary |
採用ミスマッチの防止
求職者が作成したジョブ・カードを選考過程で活用することで、企業は応募者の職務経験やスキル、キャリアに対する考え方をより深く理解することができます。これにより、単なる履歴書や職務経歴書だけでは見えにくい適性や価値観を把握しやすくなります。 結果として、入社後の「こんなはずではなかった」というミスマッチを減らし、早期離職の防止につながります。また、採用基準が明確になることで、採用活動全体の効率化も期待できます。助成金の活用によるコスト削減
ジョブ・カードを活用した職業訓練やキャリアコンサルティングを実施する企業は、厚生労働省が管轄する各種助成金制度の対象となる場合があります。代表的なものに「人材開発支援助成金」や「キャリアアップ助成金」などがあります。 これらの助成金を活用することで、人材育成にかかる費用負担を軽減し、より積極的に従業員の能力開発に取り組むことが可能になります。ただし、助成金の受給には一定の要件があるため、事前に詳細を確認することが重要です。【企業向け】ジョブ・カード導入のデメリットと注意点
ジョブ・カード制度の導入は企業にとって多くのメリットをもたらす可能性がある一方で、いくつかのデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることで、制度の形骸化を防ぎ、効果的な運用を目指すことが重要です。導入・運用にかかる時間と手間
ジョブ・カードを全社的に導入し、運用していくためには、従業員への説明会の実施、様式の準備、記入のサポート、キャリアコンサルタントとの連携、面談時間の確保など、人事担当者や管理職に相応の時間と手間がかかります。特に中小企業など、リソースが限られている場合には負担が大きくなる可能性があります。 この対策としては、スモールスタートで一部の部署から試行的に導入したり、外部の専門家( キャリアコンサルタント など)のサポートを活用したりすることが考えられます。従業員の評価への直接的な連動の難しさ
ジョブ・カードは本来、従業員のキャリア形成を支援し、能力開発を促すためのツールであり、直接的な人事評価や処遇決定の材料として設計されていません。ジョブ・カードの内容を短絡的に評価に結びつけてしまうと、従業員が正直なキャリアプランや弱みを記述しにくくなり、制度本来の目的が損なわれる可能性があります。 評価とは切り離し、あくまで能力開発やキャリア支援のためのコミュニケーションツールとして位置づけることが重要です。形骸化させないための継続的な働きかけの必要性
ジョブ・カード制度を導入しても、単に書類を作成させるだけで終わってしまっては、その効果は期待できません。定期的な更新の機会を設けたり、ジョブ・カードを活用したキャリア面談を継続的に実施したりするなど、制度を形骸化させないための仕組みづくりと、経営層や管理職からの積極的な働きかけが不可欠です。 従業員がジョブ・カードの意義を理解し、主体的に活用するようになるためには、企業側の根気強いサポートとアプロ―トが求められます。企業におけるジョブ・カードの具体的な活用場面
企業がジョブ・カード制度を導入する際、その活用方法は多岐にわたります。従業員のキャリア形成支援から組織開発まで、様々な場面で効果を発揮する可能性を秘めています。ここでは、代表的な活用場面をいくつか紹介します。新入社員研修・フォローアップ研修での活用
新入社員研修の初期段階でジョブ・カードを作成させることは、社会人としてのキャリア意識を早期に醸成するのに役立ちます。学生時代の経験を振り返り、これからどのような社会人になりたいか、どのようなスキルを身につけたいかを考えるきっかけとなります。上司や先輩社員がその内容を基に面談を行うことで、きめ細やかな育成支援が可能になります。キャリア面談・1on1ミーティングでの活用
定期的に行われる上司と部下のキャリア面談や1on1ミーティングの際に、ジョブ・カードを共通の資料として活用することで、より具体的で建設的な対話が期待できます。部下は自身のキャリアプランや課題を整理して伝えやすくなり、上司は部下の意向を正確に把握し、適切なアドバイスやサポートを提供しやすくなります。 これにより、従業員のモチベーション向上や、エンゲージメント強化にもつながります。人事評価制度との連携
前述の通り、ジョブ・カードを直接的な評価ツールとすることは避けるべきですが、人事評価のプロセスにおいて、自己評価や目標設定の参考資料として活用することは有効です。ジョブ・カードに記述されたキャリア目標や習得スキルが、評価期間中の行動や成果とどのように結びついているかを確認することで、より納得感のある評価とフィードバックが可能になります。 ただし、その際はあくまで本人のキャリア支援が主目的であることを明確にし、評価のためのツールとして従業員にプレッシャーを与えない配慮が必要です。
このような連携により、評価制度が単なる査定だけでなく、従業員の成長支援とキャリア形成を促す仕組みとして機能することが期待できます。
配置転換・異動時の活用
従業員の配置転換や異動を検討する際に、ジョブ・カードは本人のキャリア志向や保有スキルを把握するための重要な情報源となります。本人の希望や適性を考慮した上で配置を行うことで、異動後の早期の戦力化やモチベーション維持が期待できます。 また、異動先の部署で新たに必要となるスキルや知識をジョブ・カードを通じて明確にし、計画的なOJTや研修を実施することも可能です。【個人向け】ジョブ・カード作成・活用のメリット
ジョブ・カードは、企業だけでなく、個人のキャリア形成においても非常に有効なツールです。自身のキャリアを主体的に考え、行動していく上で、多くのメリットを享受することができます。自己理解の深化とキャリアプランの明確化
ジョブ・カードを作成する過程で、これまでの職務経験、学習歴、保有スキルなどを振り返ることは、自分自身の強みや弱み、価値観、興味・関心の方向性などを客観的に把握する良い機会となります。これにより、漠然としていた自己イメージが具体的になり、自己理解が深まります。 そして、その自己理解に基づいて、将来どのようなキャリアを築いていきたいのか、そのためには何をすべきかといった具体的なキャリアプランを描きやすくなります。目標が明確になることで、日々の仕事へのモチベーション向上にもつながります。職業能力の証明としての活用
ジョブ・カードは、自身の職業能力や経験を具体的に示すことができる公的な様式です。特に、職務経歴だけでは伝えきれない訓練歴や実務で培った能力などを「職業能力証明シート」としてまとめることで、転職活動や再就職活動の際に、自身のスキルを効果的にアピールする材料となります。 また、フリーランスとして活動する際や、新たな分野に挑戦する際にも、これまでの実績を客観的に示すツールとして役立ちます。
| ジョブ・カードが職業能力証明に役立つ場面 | 具体的な活用例 |
|---|---|
| 転職・再就職活動 | 応募書類(履歴書・職務経歴書)の補足資料として提出し、面接時の自己PRに活用する |
| 職業訓練の申込 | 訓練受講の目的や意欲を伝え、自身の適性をアピールする |
| キャリアチェンジ | 未経験の職種・業界へ挑戦する際に、これまでの経験で培ったポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)や学習意欲を具体的に示す |
| 社内でのキャリアアップ | 異動希望や昇進・昇格の際に、自身の能力や実績を上司や人事担当者に伝えるための客観的な資料として活用する |
| フリーランスとしての活動 | これまでの実績や専門性をクライアントに提示し、信頼を得るためのポートフォリオの一部として活用する |
キャリアコンサルティングを受ける機会の獲得
作成したジョブ・カードを活用して、キャリアコンサルタントによる専門的なキャリアコンサルティングを受けることが出来ます。 また、自分自身で作成することが難しい場合には、キャリアコンサルティングの機会を通して、キャリアコンサルタントと一緒に作成を進めることが出来ます。キャリアコンサルタントは、キャリア形成に関する専門知識やスキルを有しており、ジョブ・カードを基に個人の悩みや課題の整理、目標設定の支援、具体的な行動計画の策定などをサポートしてくれます。 客観的な視点からのアドバイスや情報提供を受けることで、一人では気づかなかった新たな可能性を発見したり、キャリアに関する不安を解消したりするきっかけが得られます。
関連記事: キャリアコンサルタントの活用企業はどのくらい?役割や仕組みの導入メリットも紹介 | キャリアコンサルタントLibrary |