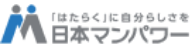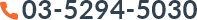キャリアコンサルタントLibrary
人の力になりたいという気持ちが原動力!それが社会の役に立つのがキャリアコンサルタント資格です!!
事例紹介 その他
キャリアコンサルタントは役に立たない?真の価値と効果的な活用法とは

キャリアコンサルタントは役に立たない?真の価値と効果的な活用法とは
「キャリアコンサルタントの資格を取っても意味がないのでは?」「キャリアコンサルタントは役に立たないと聞くけれど本当?」こうした疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。国家資格であるキャリアコンサルタントは、取得するための費用や時間がかかる一方で、「役に立たない」という評価を耳にすることもあります。
本記事では、キャリアコンサルタントの資格が役に立たないと言われる理由を客観的に分析し、実際には誰にとって、どのような場面で価値を発揮するのかを具体的に解説します。資格取得を検討している方にとって、判断材料となる情報をお届けします。
\実際はどうなの?/
有資格者インタビューはこちら▶キャリアコンサルタントとは?資格の概要と役割
キャリアコンサルタントは、2016年4月に職業能力開発促進法によって国家資格として定められた、比較的新しい資格です。
職業能力開発促進法 第2条第5項ではキャリアコンサルタントの定義として次のように 定めています。 「労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行う専門家」 キャリアコンサルタントの主な役割をまとめると以下のようになります。
• 職業の選択や転職に関する相談対応
• 職業生活設計のサポート
• 職業能力開発向上のための支援
• キャリア形成に関する助言・指導
職業や今後のキャリアに関する役割が中心ですが、これらに留まらず、その人らしい多様な生き方や働き方の実現を支援する専門家としての役割を担います。
キャリアコンサルタントの活躍の場は多岐にわたり、企業の人事部門、就職・転職支援機関、教育機関のキャリアセンター、公共職業安定所(ハローワーク)などが主な活動領域です。独立して個人のキャリア相談を受けるフリーランスとしての道もあります。
▷関連リンク:
キャリアコンサルタント資格の種類を徹底解説!受験資格や難易度の違いは? | キャリアコンサルタントLibrary |
キャリアコンサルタントの資格が役に立たないと言われる3つの理由
キャリアコンサルタントが「役に立たない」と言われる背景には、いくつかの理由があります。まずはそれらを客観的に見ていきましょう。資格がなくても就職支援の仕事に就ける
キャリアコンサルタントが役に立たないと言われる最大の理由は、この資格が「業務独占資格」ではなく「名称独占資格」であることです。医師や弁護士のように、資格がないと業務を行えないわけではありません。
実際、人材紹介会社のキャリアアドバイザーや企業の人事担当者の中には資格を持たずにキャリア支援業務を行っている方もいます。特に民間企業では、資格の有無よりも実務経験やコミュニケーション能力を重視する傾向があります。
資格取得までに多大な費用と時間がかかる
キャリアコンサルタントの資格取得には、相応の費用と時間が必要です。特に実務経験の少ない方は、まず厚生労働大臣が認定する養成講座(150時間程度)を受講することをお勧めします。
養成講座の受講料は提供元養成機関によって異なりますが、20万円から45万円程度が相場です。
養成講座を受講する場合、資格取得までにそれに加えて次のような費用がかかります。
|
項目 |
費用 |
|
養成講座受講料 |
約20〜45万円 |
|
試験受験料 |
38,800円(学科試験:8,900円、実技試験:29,900円) |
|
登録費用 |
17,000円(登録免許税:9,000円、登録手数料:8,000円) |
養成講座の受講に加え、試験に向けた学習時間も必要です。こうした費用や時間の投資に見合うリターンがあるのか疑問視する声も少なくありません。
資格取得がすぐに就職や収入に直結しない
「キャリアコンサルタントの資格を取得すれば、未経験でもすぐに独立できる」「高収入の仕事に就ける」といった期待を持つ方もいるかもしれません。しかし実際には、資格取得がすぐに就職や収入アップに直結するとは限りません。
労働政策研究・研修機構の調査によると、キャリアコンサルタント登録者のうち、「キャリアコンサルタント」を専任・専業として活動している人の割合は約4割程度で、そのうち半数以上が非正規雇用という実態があります。また同調査では、「キャリアコンサルタントとしての活動が多く、かつ年収も多いキャリアコンサルタントは少ない」という問題点も指摘されています。
このように、資格を取得したからといって、すぐに安定した職業として成立するわけではない現実が、「役に立たない」という評価につながっているといえるでしょう。
【出典】労働政策研究・研修機構(JILPT):
労働政策研究報告書No.227「第2回キャリアコンサルタント登録者の活動状況等に関する調査」
キャリアコンサルタント資格が実際に役立つ4つの場面
一方で、キャリアコンサルタントの資格は、特定の場面で大いに価値を発揮します。どのような状況で役立つのか、具体的に見ていきましょう。企業内でのキャリア支援業務
企業内では、従業員のキャリア開発支援や定着率向上のために、キャリアコンサルティングの需要が高まっています。特に近年は「セルフ・キャリアドック」と呼ばれる定期的に面談やキャリア研修などを行うことで、従業員のキャリア形成を促進・支援する取り組みの導入が進んでいます。
厚生労働省が推進するセルフ・キャリアドックでは、原則として面談を実施する者はキャリアコンサルタントの国家資格またはキャリアコンサルティング技能検定を保有していることが推奨されています。こうした制度の普及により、企業内でキャリアコンサルタント資格の価値は高まりつつあります。
企業の人事部門あるいは、管理職がキャリアコンサルタントの資格を持つことで、社員面談の質が向上し、より深いコミュニケーションが可能になったという声も多く聞かれます。
▷関連リンク:
キャリアコンサルタントの活用企業はどのくらい?役割や仕組みの導入メリットも紹介 | キャリアコンサルタントLibrary |
就職支援・人材紹介会社での活用
就職支援機関や人材紹介会社でも、キャリアコンサルタントの資格を活かすことができます。
また、公的機関での採用においては、キャリアコンサルタント資格の保有が必須、もしくは優遇されるケースが増えています。
例えば、ハローワーク、ジョブカフェ、地域若者サポートステーション、就労支援センターなどでは、キャリアコンサルタントの資格を持つ専門家による相談業務が行われています。これらの機関では、さまざまな背景を持つ求職者に対して、適切な支援を提供するための専門知識が求められます。国としてもより専門性に裏付けされた支援をしようという表れと言えるでしょう。
また、人材紹介会社においても、転職希望者に対して専門的なカウンセリングを提供できるスキルは大きな強みになります。特に昇進や昇給を目指す場合、資格保有がポジティブに評価されるケースも増えています。
教育機関での学生支援
大学や専門学校などの教育機関のキャリアセンターでは、学生に対する就職支援やキャリア教育の重要性が高まっています。こうした場でも、キャリアコンサルタントの専門知識は大いに活用ができます。
キャリア教育の一環として、学生の自己理解を促し、将来のキャリアプランを考えるサポートをする役割は、専門的なスキルを持ったキャリアコンサルタントだからこそ貢献ができる分野です。履歴書・エントリーシートの作成支援、面接指導、インターンシップ先の選定などにおいて、体系的な知識に基づいた支援が可能になります。
教育機関の求人においても、キャリアコンサルタントの資格保有者を優遇する傾向が見られ、専門性を証明するツールとして役立ちます。
独立・起業やフリーランスとしての活動
キャリアコンサルタントの資格は、独立してキャリアコンサルティング業務を行う際にも信頼性の担保として大きな価値を持ちます。国家資格を保有していることで、相談者から信頼を得やすくなり、サービスの差別化が図れる可能性があります。
フリーランスのキャリアコンサルタントとして活動する場合、キャリアコンサルタントと利用者のマッチングサービスへの登録が一つ方法として挙げられます。このサービスを通じて、就職支援施設でのセミナー講師や個別相談などの仕事を受注できるケースもあります。
また、企業研修の講師、キャリア教育の専門家としての活躍の道も広がります。特定の分野や対象者に特化した専門性を高めることで、差別化を図り、独自のポジションを確立することも可能です。
\資格取得後の活用事例もご紹介/
キャリアコンサルタント養成講座説明会はこちら▶キャリアコンサルタント資格取得の5つのメリット
キャリアコンサルタントの資格取得には、単に仕事を得るだけではない様々なメリットがあります。以下に主な5つのメリットを紹介します。①専門的な知識とスキルの獲得
キャリアコンサルタントの養成講座では、キャリア形成支援に必要な広範な知識とスキルを体系的に学ぶことができます。例えば、以下のような内容が含まれます。
• キャリア理論(シャイン、ホランド、クランボルツなど)
• カウンセリング理論(来談者中心療法、交流分析など)
• 労働市場や雇用情勢に関する知識
• 労働関連法規の理解
• メンタルヘルスの基礎知識
• キャリアコンサルティングの技法・実践方法
これらの知識は、キャリア支援の実務に直接活かせるだけでなく、人事業務全般や管理職としての部下育成にも応用できる汎用性の高いものです。
②相談者からの信頼性の向上
国家資格を持つことで、相談者からの信頼を得やすくなるメリットがあります。特に個人のキャリアという繊細な問題を扱う場合、「国から認められた専門家」であるという肩書きは、相談者に安心感を与えることができます。
「キャリアコンサルタント」という資格名は、その役割が理解されやすく、「この人はキャリアについての専門家なんだ」と認識してもらいやすい点も強みです。
③キャリアアップや転職の選択肢の拡大
キャリアコンサルタントの資格を持つことで、現職でのキャリアアップや転職時の選択肢が広がる可能性があります。特に人事部門や人材関連業界では、専門性の証明として評価されるケースが増えています。
例えば、現在の会社の人事部門への異動を希望する場合や、人材業界への転職を考える場合、資格保有はアドバンテージとなる可能性があります。
また、企業によってはキャリアコンサルタント資格に対する手当を支給しているところもあり、収入アップにつながる場合もあります。
④継続的な学びと人脈形成
キャリアコンサルタントの資格取得後は、5年ごとに更新が必要です。その際には、知識講習(8時間以上)と技能講習(30時間以上)の受講が義務付けられています。
一見、負担に感じるかもしれませんが、この仕組みによって最新の労働市場動向やキャリア開発理論、カウンセリング手法などを継続的に学び続けることができます。変化の激しい現代社会において、常に最新の知識を持ち続けられる点は大きなメリットといえるでしょう。
さらに、講習やキャリアコンサルタント有資格者のコミュニティに参加することで、同じ志を持つ仲間とのネットワークが広がります。こうした人脈は、情報交換や仕事の紹介など、様々な形で将来の糧となります。
⑤自分自身のキャリア形成への応用
キャリアコンサルタントの学びは、相談者のためだけでなく、自分自身のキャリア形成にも大いに役立ちます。キャリア理論や自己分析の手法を学ぶことで、自分のキャリアを客観的に見つめ直すきっかけになります。キャリアコンサルタントの将来性と需要の高まり
キャリアコンサルタントの資格は「役に立たない」と言われることもありますが、社会情勢や国の政策を見ると、将来的な需要は高まることが予想されます。働き方の多様化による需要増加
近年、働き方の選択肢は大きく広がっています。終身雇用制度の崩壊、副業・兼業の広がり、フリーランスという働き方の一般化など、キャリア選択の自由度が高まっている一方で、その分だけ悩みや不安も増加しています。
このような状況下で、適切なキャリア支援の必要性はますます高まっています。キャリアの選択肢が多様化するほど、自分に合った道を見つけるための専門的なサポートが求められるようになるでしょう。
さらに、人生100年時代を迎え、従来の「教育→仕事→引退」という単線型のライフコースから、複数のキャリアを経験する「マルチステージ」の人生設計が重要になっています。長期化する職業人生において、定期的なキャリアの棚卸しや再設計の需要が高まることが予想されます。
セルフ・キャリアドックなど国の推進施策
厚生労働省は、企業におけるキャリア形成支援の仕組みとして「セルフ・キャリアドック」を推進しています。これは、企業が従業員のキャリア形成を支援するため、定期的なキャリアコンサルティングやキャリア研修などを計画的に実施する取り組みです。
セルフ・キャリアドックの導入にあたっては、キャリアコンサルタントの資格保有者が面談を担当することが原則として必須とされています。今後、セルフ・キャリアドックを導入する企業が増えるにつれて、キャリアコンサルタントの需要も高まることが期待されます。
厚生労働省は「キャリア支援施策の柱としてキャリアコンサルティングの普及策を積極的に推進する」との方針を打ち出しており、国の後押しによる普及も期待できるでしょう。
【参考】厚生労働省「
働く環境の変化に対応できるキャリアコンサルタントに関する報告書
」
リスキリング時代におけるキャリア相談の重要性
AI(人工知能)やロボティクスなどのテクノロジーの急速な発展により、多くの職業が変容しつつあります。経済産業省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」などに見られるように、新しいスキルを身につけて別の職種や業界に移る「リスキリング」の重要性が高まっています。
リスキリングを成功させるためには、自分の強みや興味・関心の方向性を明確にし、将来性のある分野を見極める必要があります。そのためのサポート役として、キャリアコンサルタントの役割は重要度を増しています。
経済産業省のリスキリング支援事業では、キャリアコンサルタントなどの専門家によるキャリア相談が重要な要素として位置づけられており、今後もこうした政策面からの後押しが期待できるでしょう。
キャリアコンサルタントとして活躍する人の実例
日本マンパワーのホームページでは、養成講座を修了し、キャリアコンサルタントとして活動している方々のインタビュー記事を多数掲載しています。
キャリアコンサルタントの資格が実際にどのように活かされているのか、具体的な事例を見てみましょう。
1.企業内人事での活用事例
https://www.nipponmanpower.co.jp/cc/interview/detail/38
2.人材ビジネス関連での活用事例
https://www.nipponmanpower.co.jp/cc/interview/detail/46
3.行政関連での事例
https://www.nipponmanpower.co.jp/cc/interview/detail/49
4.学校・教育関連での事例
https://www.nipponmanpower.co.jp/cc/interview/detail/50
5.フリーランスでの事例
https://www.nipponmanpower.co.jp/cc/interview/detail/62
まとめ
キャリアコンサルタント資格は人事・教育・就業支援等の業務に携わる方はもちろんのこと、 家族や、友人との日常のコミュニケーションにおいても活かすことが可能です。 また、自分自身のキャリアについて迷ったりした場合にも、学んだことをベースにしながら、 より良い意思決定の一助になるということもあります。 自身の状況・長期的な視点で、キャリアコンサルタント資格の取得についてぜひご検討ください。キャリアコンサルタント資格取得を目指すなら日本マンパワーの養成講座がおすすめ
キャリアコンサルタントを目指すと決めた方は、養成講座を受講して受験資格を得る方法がおすすめです。
日本マンパワーのキャリアコンサルタント養成講座は厚生労働大臣の認定講習で、受講・修了すると国家資格キャリアコンサルタントの受験資格が得られます。特徴は以下の通りです。
日本マンパワーの養成講座の特徴
• 成長支援の考え方が学べるわかりやすいテキストや選べる学習スタイル
• 振替制度やオンライン自習室などの充実したサポート体制
• 専門講座を修了し試験に合格した実践経験豊富な講師陣
日本マンパワーの講座は、「通信教育」と「スクーリング」の2つがセットです。受験安心サポートも充実しています。
| 通信教育(eラーニング) | ・テキスト ・テキスト解説映像 |
| スクーリング(通学・オンライン) | ・講義 ・ロールプレイ&ワーク |
| 受験安心サポート | ・講師常駐のオンライン自習室 ・実践力強化教材 |
通信教育では、解説映像とテキストでキャリアコンサルタントに求められる知識を体系的に習得できます。
一方、スクーリングは、グループワークやロールプレイなどを通じた実習が中心です。「通学クラス」と「オンラインクラス」から、ご自身に合った学習スタイルを選択でき、キャリアコンサルタントに必要な技能を体感しながら身につけられます。
また、受験安心サポートとして「オンライン自習室」と「実践力強化教材」があり、講師常駐のオンライン自習室は、定期的に開室しています。実践力強化教材は、現場でも必須の知識・技能を更に高められる点が特徴です。
さらに、試験合格に向けて活用できる教材が揃っているだけでなく、合格後も実務に活かせる情報提供を行っています。
日本マンパワーでは、講座の特徴を短時間で知りたい方向けに、オンライン開催の説明会もご用意しています。キャリアコンサルタント資格に興味のある方や養成講座の特徴を詳しく知りたい方は、ご都合の良い開催地・時間帯で日本マンパワーの講座説明会にご参加ください。