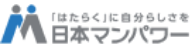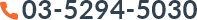キャリアコンサルタントLibrary
人の力になりたいという気持ちが原動力!それが社会の役に立つのがキャリアコンサルタント資格です!!
キャリアコンサルタントとは
キャリアコンサルタントのあるべき姿とは?倫理綱領の内容を徹底解説

「キャリアコンサルタント倫理綱領」とは、キャリアコンサルタントとして守るべき心構えや行動規範を示した文書を指し、
試験でも頻出の項目です。内容に目を通しておき、意図を理解しておきましょう。
本記事では、キャリアコンサルタント倫理綱領の概要や制定の背景、改正内容、学習のポイントなどを紹介します。
なお、キャリアコンサルタントに関する最新の情報を収集する手段としては、説明会への参加がおすすめです。
日本マンパワー(当社)では、キャリアコンサルタント養成講座を開設しており、講座に関する無料の説明会を3種類
ご用意しています。興味がある方はぜひご参加ください。
キャリアコンサルタント養成講座説明会について詳しくはこちら
キャリアコンサルタント養成講座のお申込みはこちら
キャリアコンサルタントのあるべき姿とは
国のキャリアコンサルタント制度は、2002年8月にスタートしました。キャリアコンサルティング実施のために必要な能力体系と
モデルカリキュラムの訓練時間が、国によって制定されています。
2004年、特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会を中心に指定団体が集まり、
「キャリアコンサルタント行動憲章」を設定されました。行動憲章が設定された目的は、キャリアコンサルタントの行動原則を示し、
行動規範の明確化とキャリアコンサルティングの普及を目指すことでした。
その後、2008年に、同協議会によって、「キャリアコンサルタント倫理綱領」が制定されました。
ここには、キャリアコンサルタントのあるべき姿が示され、2016年、2024年に改正されています。(詳細は後述します。)
「キャリアコンサルタント倫理綱領」とは
「キャリアコンサルタント倫理綱領」とは、キャリアコンサルタントとして守るべき心構えや規範などの基本的な内容を 明文化した文書です。
先述の通り、2008年に制定されたキャリアコンサルタント倫理綱領は、2度の改正を経て現在の内容となっています。
キャリアコンサルタントの仕事は、相談者の今後の人生を大きく左右する職業やキャリア形成に関して専門家として関わり、
相談者にとってより良い方向へと導くことです。ひとつの言動が、相談者の決断に大きな影響を及ぼす可能性があるため、
高い職業倫理を持って職務にあたる必要があります。
キャリアコンサルタント倫理綱領の制定から改正に至る背景
2007年に、当時の民間養成団体と厚生労働省がともに特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会を立ち上げました。
キャリアコンサルタントの育成体系について度重なる議論を経て、2008年にキャリアコンサルタント倫理綱領が制定されました。
2008年は、キャリアコンサルティング技能検定が国家検定としてスタートした年でもあります。
その後、2016年に大きな改正が行われました。改正には、改正職業能力開発促進法で、キャリアコンサルタントの国家資格化及び
登録制度が創設された背景があります。キャリアに関する専門家として、一層高い倫理感を持って職務にあたる姿勢が
求められます。
そして、2024年に2回目の改正が行われています。前回の改正から現在に至るまでの間には、働き方改革やDXの推進、
テレワークの拡大、リスキリングの重要性の高まりなど、多くの社会状況の変化がありました。
2023年12月に厚生労働省が公表した「キャリアコンサルタント登録制度等に関する検討会報告書」によると、
「キャリアコンサルタントへの期待は高まり、責任はより重くなった」とされています。
2024年改定の倫理綱領では、キャリアコンサルティングの重要性の高まりや、多様性の尊重などに関する記載が追記された他、
自己研鑽の項には、スーパーバイザーという言葉が明記されるなど、最新の情報技術の修得・活用に関する内容も
追記されています。
キャリアコンサルタント倫理綱領の制定から改正に至る背景
2007年に、当時の民間養成団体と厚生労働省がともに特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会を立ち上げました。
キャリアコンサルタントの育成体系について度重なる議論を経て、2008年にキャリアコンサルタント倫理綱領が制定されました。2008年は、キャリアコンサルティング技能検定が国家検定としてスタートした年でもあります。
その後、2016年に大きな改正が行われました。改正には、改正職業能力開発促進法で、キャリアコンサルタントの国家資格化及び登録制度が創設された背景があります。キャリアに関する専門家として、一層高い倫理感を持って職務にあたる姿勢が求められます。
そして、2024年に2回目の改正が行われています。前回の改正から現在に至るまでの間には、働き方改革やDXの推進、テレワークの拡大、リスキリングの重要性の高まりなど、多くの社会状況の変化がありました。
2023年12月に厚生労働省が公表した「キャリアコンサルタント登録制度等に関する検討会報告書」によると、「キャリアコンサルタントへの期待は高まり、責任はより重くなった」とされています。
2024年改定の倫理綱領では、キャリアコンサルティングの重要性の高まりや、多様性の尊重などに関する記載が追記された他、自己研鑽の項には、スーパーバイザーという言葉が明記されるなど、最新の情報技術の修得・活用に関する内容も追記されています。
キャリアコンサルタント倫理綱領の内容
倫理綱領は、以下の4つのパートで構成されています。学習にあたっては、それぞれのパートに記載されている内容の趣旨を理解しましょう。
- ・序文
- ・前文
- ・基本姿勢・態度
- ・行動規範
それぞれの詳細を解説します。
出典: 特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会「キャリアコンサルタント倫理綱領」序文|キャリアコンサルタント倫理綱領の改正趣旨
序文には、2024年の改正の趣旨が記載されています。社会環境の変化に伴い、キャリアコンサルタントへの期待や社会的責任が高まっていると述べたうえで「倫理観と専門性の維持向上」及び「自らの人間性を磨き、矜持と責任感を持ち、自己研鑽に励む」重要性が明記されています。
前文|キャリアコンサルタントの職務と使命
「職業能力開発促進法に則り、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うこと」がキャリアコンサルタントの職務です。 こうした記載から、キャリアコンサルタントの職務は、相談者の不安・悩みに寄り添う支援はもちろんのこと、相談者自身が自分今後のキャリアを主体的に考えられるように促し、相談者自身のとって望ましい方向へ支援することが重要な役割であることがわかります。 また、使命に関しては「相談者のキャリア形成の支援と、延長にある組織や社会の発展への寄与を実現する」とされています。キャリア形成の支援を通じて、組織や社会の発展への貢献が求められている点を理解しましょう。
第1章|基本姿勢・態度
第3条「社会的信用の保持」では、「キャリアコンサルタントは、常に公正な態度を持って職責を果たし、専門職として、相談者、依頼主、他の分野・領域の専門家や関係者及び社会の信頼に応え、信用を保持しなければならない」とされています。
キャリアコンサルタントが専門家として社会の信頼に応えなければならない存在であるとがわかります。
第2章|行動規範
第8条「任務の範囲・連携」には「キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングを行うにあたり、自己の専門性の範囲を自覚し、範囲を超える業務や自己の能力を超える業務の依頼を引き受けてはならない」とあります。
業務の遂行過程では、自分の知識やスキルだけでは対応できない事案に遭遇する場合があるでしょう。そういう場合は1人で解決を目指さず、他の専門家と連携しながら相談者の問題解決にあたることが求められています。
国家試験に向けたキャリアコンサルタント倫理綱領の学習ポイント

倫理綱領は、試験の頻出項目です。倫理綱領の学習のポイントは、以下の2つです。
・国家資格キャリアコンサルタント試験の過去問をチェックする
それぞれの詳細を解説します。
学科試験や受験資格については以下の記事で紹介しているため、併せてご覧ください。
▷関連記事:
キャリアコンサルタント試験の学科試験とは?形式・出題範囲や合格に向けた対策を紹介
▷関連記事:
キャリアコンサルタント試験の受験資格は?未経験から国家資格取得を目指す方法も解説
キャリアコンサルタント倫理綱領を一通り確認して意図を理解する
倫理綱領は、キャリアコンサルティング協議会のホームページから全文を閲覧できます。全体で6ページほどの簡潔な文書のため、全てに目を通しましょう。
試験では、倫理綱領の趣旨を理解していなければ解けない問題も出題されます。単に条文を暗記せず、背景や意図も理解しておく必要があります。
独学で全てを理解するには時間がかかるため、改正の背景や趣旨を深く学ぶには、養成講座の受講も選択肢のひとつです。
キャリアコンサルタント養成講座説明会について詳しくはこちら
キャリアコンサルタント養成講座のお申込みはこちら
国家資格キャリアコンサルタント試験の過去問をチェックする
日本キャリア開発協会及びキャリアコンサルティング協議会のホームページには、過去3回分の試験問題が掲載されています。傾向を掴むためにも、過去問を解きましょう。
出題は、4つの選択肢の中から倫理綱領の内容に合致したものを選ぶ形式です。実際の問題に多くあたると、倫理綱領のポイントが理解しやすくなるでしょう。
過去問は、日本キャリア開発協会の「過去問題」やキャリアコンサルティング協議会の「過去問題/学習情報」で確認できます。
今後のキャリアコンサルタント活動に求められること
社会環境の変化と共に、キャリアコンサルタントに求められる内容も変化しています。
今後、キャリアコンサルタント活動に求められることは、主に以下3つです。
- ・キャリアコンサルタント自身の自己成長
- ・専門家としての客観的、多角的な視点と判断力
- ・ネットワーク形成力
キャリアコンサルタント自身の自己成長
キャリアコンサルティングとは、単に適職を紹介したり、就職情報を提供したりするだけではなく、相談者の自分らしい生き方、生涯にわたる職業生活設計に関わる支援をすることです。
理想的な支援を実現するには、相談者の異なる生き方や考え方を理解し、未来に向けた主体的な選択を支援するための本質的な知識や技能を磨く必要があります。
相談者ひとりひとりとの関わりを通して、自己成長を続けられるよう努力しましょう。
専門家としての客観的、多角的な視点と判断力
技術革新や産業構造の転換に伴う労働移動の増加など、労働者を取り巻く雇用環境は大きく変化しています。
働く人やこれから働こうとする人が適切なキャリア形成を図るには、業務に必要な職業能力に関する情報や教育訓練に関する情報などを十分に活用した支援が不可欠です。
キャリアコンサルタントは、キャリアに関する専門家として客観的かつ多角的な視点から相談者をサポートする役割を担っています。
ネットワーク形成力
相談者に対して安定的に質の高いキャリアコンサルティングを提供するには、キャリアコンサルタント自身が専門性の限界を理解し、他の分野や領域の専門家及び関係者とのネットワークを構築していく姿勢が大切です
必要な情報をリサーチしながら、相談者がより良い選択をできるよう、他の専門家などとも連携して支援にあたりましょう。
キャリアコンサルタントを目指すなら日本マンパワーの養成講座がおすすめ
キャリアコンサルタントを目指すなら、試験対策だけでなく、あるべき姿を理解する必要があります。また、実践力のあるキャリアコンサルタントを目指すなら、キャリアコンサルティングの本質を理解し、行動に移す姿勢が大切です。
あるべき姿やキャリアコンサルティングへの理解を深めたい場合は、養成講座の受講も選択肢のひとつです。日本マンパワーの「キャリアコンサルタント養成講座」は厚生労働大臣の認定講習で、受講・修了すると国家資格キャリアコンサルタントの受験資格が得られます。特徴は以下の通りです。
日本マンパワーの養成講座の特徴
- ・成長支援の考え方が学べるわかりやすいテキストや選べる学習スタイル
- ・振替制度やオンライン自習室などの充実したサポート体制
- ・専門講座を修了し試験に合格した実践経験豊富な講師陣
日本マンパワーの講座は、「通信教育」と「スクーリング」の2つがセットです
さらに、受験安心サポートも充実しています。| 通信教育(e-ラーニング) | ・テキスト ・テキスト解説映像 |
| スクーリング(通学・オンライン) | ・講義 ・ロールプレイ&ワーク |
| 受験安心サポート | ・講師常駐型のオンライン自習室 ・実践力強化教材 |
通信教育では、解説映像とテキストでキャリアコンサルタントに求められる知識を体系的に習得できます。
一方、スクーリングは、グループワークやロールプレイなどを通じた実習が中心です。「通学クラス」と「オンラインクラス」から、ご自身に合った学習スタイルを選択でき、キャリアコンサルタントに必要な技能を体感しながら身につけられます。
識の定着を図るための確認テスト等コンテンツが充実しており、試験合格に向けて活用できる教材が揃っているだけでなく、合格後も実務に活かせる情報提供を行っています。
キャリアコンサルタント資格に興味のある方や養成講座の特徴を詳しく知りたい方は、ご都合の良い開催地・時間帯で無料の講座説明会にご参加ください。講座の特徴を短時間で知りたい方向けに、オンライン開催の説明会もご用意しています。
キャリアコンサルタント養成講座説明会について詳しくはこちら
キャリアコンサルタント養成講座のお申込みはこちら
倫理綱領を学んでキャリアコンサルタントの本質を理解しよう
キャリアコンサルタント倫理綱領には、キャリアコンサルタントが自らを律するための「基本姿勢・態度」が記載されています。そして、相談者との関係で遵守すべき「職務遂行上の行動規範」を示しています。
キャリアコンサルタントを目指す場合は、あるべき姿を理解するためにも倫理綱領について学んでおきましょう。
また、キャリアコンサルタント倫理綱領は、キャリアコンサルタント試験の頻出問題です。これからキャリアコンサルタントになりたいと考えている方は、理解を深めるためにも養成講座の受講がおすすめです。まずはお気軽に説明会へご参加ください。
キャリアコンサルタント養成講座説明会について詳しくはこちら
キャリアコンサルタント養成講座のお申込みはこちら