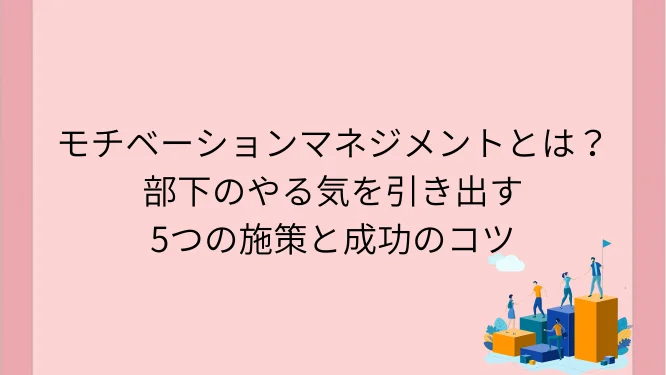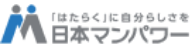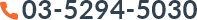部下の元気がなく、チームの雰囲気がどこか重い。会議での発言も少なく、全体の生産性が上がらない。管理職として、このような悩みを抱えてはいないでしょうか。その課題の根源には、従業員の「モチベーション」の問題が隠れているかもしれません。本記事では、従業員のやる気を引き出し、組織を活性化させる「モチベーションマネジメント」について、その基本から具体的な実践方法、成功事例までを分かりやすく解説します。
モチベーションマネジメントとは?
モチベーションマネジメントは、現代の組織運営において非常に重要な要素です。まずはその基本的な定義と、なぜ今注目されているのかについて理解を深めましょう。
従業員の意欲を引き出す重要なマネジメント手法
モチベーションマネジメントとは、従業員一人ひとりの仕事に対する「意欲」や「やる気」の源泉を理解し、それらを高めるために適切な働きかけを行うマネジメント手法のことです。 単に業務を管理するだけでなく、従業員が自発的に高いパフォーマンスを発揮できるよう、内面的な動機にアプローチすることを目的とします。これにより、従業員のエンゲージメント向上や離職防止、ひいては組織全体の持続的な成長が期待できます。
なぜ今、モチベーションマネジメントが必要なのか
現代において、モチベーションマネジメントの重要性がますます高まっている背景は深刻な人材不足です。パーソル総合研究所の調査によれば、2030年には644万人もの人手が不足すると予測されています。 このような状況下で企業が成長を続けるためには、新たな人材を確保することと同じくらい、今いる従業員一人ひとりの能力を最大限に引き出すことが不可欠です。従業員がやりがいを感じ、高い意欲で働ける環境を整えることは、企業の競争力に直結する重要な経営課題といえるでしょう。
モチベーションの2つの種類
モチベーションマネジメントを効果的に実践するためには、モチベーションが何によって生まれるのか、その種類を理解しておくことが重要です。モチベーションは大きく「外発的動機づけ」と「内発的動機づけ」の2つに分類されます。
外部からの働きかけによる「外発的動機づけ」
外発的動機づけとは、給与、昇進、他者からの評価や称賛、あるいは罰則の回避といった、外部からの働きかけによって生まれるモチベーションです。 「給料を上げるために頑張る」「上司に認められたいから成果を出す」といったケースが該当します。外発的動機づけは、即効性があり、多くの従業員に対し効果を発揮します。しかし、その効果は一時的なものにとどまりやすく、報酬を得た時点で満足してしまい、長期的な意欲の維持が難しい側面もあります。
内側から湧き出る「内発的動機づけ」
一方で、内発的動機づけとは、仕事そのものへの興味、関心、探求心、やりがい、成長実感といった、個人の内面から湧き出る欲求によって生まれるモチベーションのことです。 例えば、「この仕事を通じて新しいスキルを身につけたい」「この課題を解決すること自体が面白い」といった感情がこれにあたります。内発的動機づけは、他者からの強制を伴わないため、持続性が高く、従業員の自発的な行動や質の高いパフォーマンスにつながりやすいという特徴があります。
部下のモチベーションが低下する5つの原因
効果的な対策を講じるためには、まず何がモチベーションを低下させているのか、その原因を正しく理解する必要があります。代表的な5つの原因を見ていきましょう。
1)評価や待遇に対する不満
従業員は、自身の努力や成果が正当に評価され、適切な待遇に反映されることを期待しています。評価基準が曖昧であったり、フィードバックや説明や理由が不十分であったりすると、「頑張っても報われない」という不満が募り、仕事への意欲を大きく削いでしまいます。
2)職場の人間関係の悩み
多くの時間を過ごす職場の人間関係は、モチベーションを左右する重要な要素です。上司からの指示が高圧的に見えたり、同僚とのコミュニケーションが不足している、チーム内の不和が目立つ、といった日常の傾向が、従業員にとって大きな精神的ストレスとなります。そして、仕事への集中力や意欲を低下させる原因となります。
3)仕事内容そのものへの不満
「この仕事はつまらない」「自分の能力が活かせていない」「自分なりに工夫をするための裁量が与えられていない」と感じるなど、仕事そのものにやりがいや意義を見出せない場合、モチベーションを維持することが困難に感じられます。従業員の能力や志向と、任される業務内容との間にミスマッチがあると、不満が生じやすくなります。
4)会社の将来性やキャリアへの不安
所属する会社の将来性が見えなかったり、自身のキャリアアップの道筋が描けなかったりすると、従業員は働く目的を見失いがちになります。「このままこの会社にいて大丈夫だろうか」という不安は、日々の業務に対するモチベーションを低下させる要因となります。
5)心身の疲労の蓄積
過度な残業や休日出勤が続き、心身の休息が十分に取れない状態では、前向きな気持ちを維持することは難しくなります。慢性的な疲労は、意欲だけでなく、思考力や判断力の低下も招き、仕事の質にも悪影響を及ぼします。
モチベーションマネジメントがもたらす3つのメリット
モチベーションマネジメントに適切に取り組むことで、企業は多くのメリットを享受できます。ここでは、代表的な3つのメリットをご紹介します。
組織全体の生産性が向上する
モチベーションの高い従業員は、自発的に業務改善に取り組んだり、より高い目標に挑戦するなど、能動的に仕事を進めます。 こうした従業員が増えることで、一人ひとりのパフォーマンスが最大化され、組織全体の生産性向上に直結します。少ないリソースでも高い成果を上げられる、競争力のある組織へと変革することが可能です。
従業員の自発的な成長を促す
高いモチベーションを維持している従業員は、現状に満足することなく、自身のスキルアップやキャリア開発に意欲的です。資格取得への挑戦や新たな知識の習得など、自ら成長の機会を求めるようになります。このような自己成長への意欲は、個人の能力を高めるだけでなく、組織全体の知識やスキルの底上げにも貢献します。
人材の離職リスクを低減する
やりがいを感じ、自分の仕事が会社に貢献していると実感できる従業員は、企業へのエンゲージメント(愛着や貢献意欲)が高まります。 会社のビジョンに共感し、長期的なキャリアを考えるようになるため、安易な離職を防ぐことにつながります。優秀な人材の定着は、企業の持続的な成長にとって不可欠な要素です。
モチベーションマネジメントを実践する3つの手順
モチベーションマネジメントは、計画的に進めることが成功の鍵です。ここでは、基本的な3つのステップをご紹介します。
手順1:サーベイや面談で現状を把握する
まずは、従業員のモチベーションが現在どのような状態にあるのかを正確に把握することから始めます。従業員満足度調査(ES調査)のようなサーベイを実施して組織全体の傾向を掴むとともに、1on1ミーティングなどを通じて個々の従業員の声に耳を傾けることが重要です。 この段階で、モチベーション低下の根本的な原因に関する仮説を立てることが、後の施策の精度を高めます。
手順2:具体的な施策を立案し実行する
現状把握で見えてきた課題に基づき、具体的な施策を立案し、実行に移します。この際、評価制度や福利厚生といった「ハードアプローチ」と、職場風土や人間関係の改善といった「ソフトアプローチ」の両面から検討することが効果的です。 例えば、制度を新設するだけでなく、それが気兼ねなく利用できるような雰囲気づくりもセットで考えることが大切です。
手順3:施策の効果を検証し改善する
施策を実行した後も、継続的な取り組みが必要です。一定期間が経過した後、再度サーベイや面談を行い、施策が従業員のモチベーションにどのような影響を与えたのか効果を検証します。 想定通りの効果が出ているか、新たな課題は生まれていないかを確認し、得られた結果を元に次の改善アクションへとつなげていく、このPDCAサイクルを回し続けることが、モチベーションマネジメントを組織に定着させるうえで不可欠です。
明日から実践できる5つの具体的な施策
理論や手順を理解したところで、実際にどのような行動を起こせば良いのでしょうか。ここでは、管理職が明日からでも実践できる5つの具体的な施策を紹介します。
公平で透明性のある評価制度を構築する
従業員の不満の原因となりやすい評価制度は、公平性と透明性を担保することが極めて重要です。何が評価され、どうすれば昇進や昇給につながるのか、その基準を明確にし、全従業員に周知しましょう。また、評価結果を伝える際には、一方的な通達ではなく、評価の根拠を丁寧に説明し、本人の自己評価とすり合わせる双方向のフィードバックを心がけることが納得感を高めます。
1on1ミーティングで対話の機会を設ける
定期的に1on1ミーティングの時間を設け、部下の話に真摯に耳を傾けることは、信頼関係を築くうえで非常に効果的です。 業務の進捗確認だけでなく、キャリアの悩み、プライベートな関心事など、部下が話したいことを自由に話せる場を作りましょう。上司が自分に関心を持ち、理解しようとしてくれていると感じることは、部下の安心感と内発的動機づけにつながります。v
▶関連記事:1on1で話すことに困らない!効果的なテーマと具体的な進め方を解説 | キャリアコンサルタントLibrary |
従業員のキャリアプランに合わせた目標設定を行う
会社から一方的に押し付けられた目標ではなく、従業員本人のキャリアプランや成長したい方向性と、会社の目標とをすり合わせた上で、本人が納得できる目標を設定することが重要です。目標達成へのプロセスが、自身の成長につながると実感できることで、「やらされ仕事」ではなく「自分ごと」として、主体的に業務に取り組むようになります。
▶人事が、「キャリアコンサルタント」となり、従業員のキャリアプランの相談に乗れるようになることもお勧めです!
従業員同士が称賛しあう文化を醸成する
上司から部下への称賛だけでなく、同僚同士がお互いの良い仕事や貢献を認め、称賛しあう文化は、職場全体のモチベーションを大きく向上させます。成果だけでなく、日々の努力やプロセスにも目を向け、感謝や称賛の言葉を伝え合う習慣を作りましょう。「ピアボーナス」のような、従業員同士でインセンティブを送りあえる仕組みを導入するのも一つの手です。
働きやすい職場環境を整備する
長時間労働の是正、有給休暇の取得促進、テレワークやフレックスタイム制の導入など、従業員が心身ともに健康で、ワークライフバランスを保ちながら働ける環境を整えることは、モチベーションマネジメントの土台となります。従業員が安心して、かつ集中して業務に取り組める物理的・心理的な環境を提供することが、組織全体のパフォーマンスを支えます
モチベーションマネジメントの成功事例
最後に、モチベーションマネジメントに成功している企業の具体的な事例を2つ紹介します。自社で取り組む際のヒントにしてください。
株式会社ベネッセホールディングスの事例
株式会社ベネッセホールディングスでは、テレワークが普及する中で従業員の健康とモチベーションを維持するため、RIZAP社が提供するオンラインの健康増進プログラムを導入しました。短時間のオンライントレーニングや健康セミナーを継続的に実施した結果、参加者からは「リフレッシュできた」「気持ちがポジティブになった」という声が多く上がり、実際に「モチベーションが向上した」という回答も得られました。こうした取り組みが、従業員の働きがいの向上にも寄与しています。
【参考】https://blog.benesse.ne.jp/bh/ja/news/20201016_release.pdf
日本調剤株式会社の事例
日本調剤株式会社では、薬局スタッフの専門性とサービス品質を評価する独自の表彰制度「JP-CSアワード」を設けています。顧客アンケートなどの客観的な評価が各店舗にフィードバックされ、優れた成果を上げた店舗や社員が表彰されます。この仕組みにより、従業員は自身の頑張りが正当に評価されることを実感でき、仕事への誇りとモチベーションを高める源泉となっています。
【参考】https://www.nicho.co.jp/corporate/business/pharmacy/education/program/
まとめ
モチベーションマネジメントは、従業員一人ひとりの内面に働きかけ、その意欲と能力を最大限に引き出すための重要な取り組みです。モチベーションが低下する原因を理解し、現状把握から施策の実行、効果検証というサイクルを回しながら、自社に合った方法を見つけていくことが成功への道筋となります。本記事で紹介した施策や事例を参考に、従業員が生き生きと輝ける組織づくりを今日から始めてみませんか。