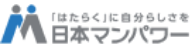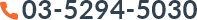キャリアコンサルタントLibrary
人の力になりたいという気持ちが原動力!それが社会の役に立つのがキャリアコンサルタント資格です!!
キャリアコンサルタントとは 事例紹介 その他
キャリア自律で未来を拓く!求められる背景と実践ステップを分かりやすく解説
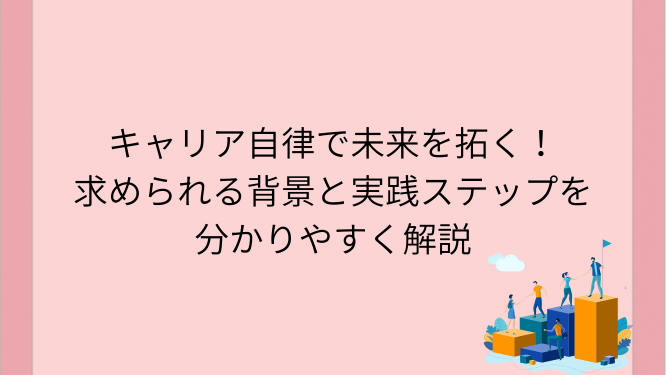
現代のビジネス環境は急速に変化しており、個人の働き方やキャリアに対する考え方も大きく変わりつつあります。かつての終身雇用が当たり前だった時代とは異なり、今や一人ひとりが自分のキャリアに責任を持ち、主体的に未来を切り拓いていく「キャリア自律」の重要性が高まっています。
本記事では、キャリア自律の基本的な考え方から、企業が従業員をどのように支援すべきか、具体的な方法や成功事例を交えて詳しく解説します。
キャリア自律とは?
キャリア自律とは、企業や組織に依存するのではなく、働く個人が自らのキャリアについて主体的に考え、責任を持って行動し、キャリアを形成していく状態を指します。
変化の激しい現代では、会社が一生のキャリアを保証するのは難しくなっています。
そのため、
●必要な知識やスキルを自分から学び続ける
●新しい環境や変化に柔軟に対応する
●自分の価値観や希望に沿った働き方を選ぶ
といった姿勢が求められます。
個人が主体的にキャリアを形成すること
キャリア自律の中心となる考え方は、キャリアの舵取りを企業ではなく自分自身が行うということです。
会社の方針にただ従うのではなく、自分の価値観や、興味、得意なことを深く理解し、「何を成し遂げたいのか」「どのような働き方をしたいのか」を繰り返し問いかけ、その答えを明確にします。
そして、そのビジョンを実現するために必要なスキルや経験を計画的に積み重ねていく――こうした主体的な行動こそが、キャリア自律の本質です。
なぜ今、キャリア自律が注目されるのか?
近年、キャリア自律という考え方が急速に広まっている背景には、社会や経済、個人の価値観における大きな変化があります。
終身雇用制度の変化と成果主義の浸透
かつての日本企業を支えてきた終身雇用や年功序列といった雇用慣行は、経済のグローバル化や低成長時代への移行とともに見直しが進んでいます。企業は年齢や勤続年数ではなく、個人の能力や成果を重視する「成果主義」へとシフトしており、従業員は与えられた仕事をこなすだけでなく、自分の市場価値を高める努力を求められるようになりました。
ジョブ型雇用の普及
特定の職務(ジョブ)に必要なスキルを持つ人材を採用・配置する「ジョブ型雇用」を導入する企業が増えています。 これは、専門性を持つ人材の確保や生産性向上を目的としています。
ジョブ型雇用の下では、従業員は自ら希望する職務に就くために、主体的に学習し、スキルを磨き続けることが不可欠となり、キャリア自律の考え方と非常に親和性が高いと言えます。
働き方の多様化と個人の価値観の変化
リモートワークやフレックスタイム、副業・兼業など、働き方の選択肢は大幅に広がりました。 これに伴い、価値観も変化し、仕事一筋ではなく、プライベートや自己実現も重視する人が増えています。自分らしいライフプランを実現するために、主体的に働き方やキャリアを選択する必要性が高まっています。
人生100年時代における長期的な視点の必要性
医療やテクノロジーの発展で、私たちはこれまで以上に長く働く時代に入りました。
一つの会社やスキルだけでキャリアを終えるのは難しく、社会の変化に合わせて学び直し(リスキリング)やキャリアチェンジを何度も行うことが当たり前になります。
だからこそ、長期的な視点でキャリア戦略を立て、学び続ける姿勢がより重要になっているのです。
企業がキャリア自律を支援するメリット
企業が従業員のキャリア自律を支援することは、一見すると離職を促進してしまうリスクがあるように思えるかもしれません。しかし、実際には企業にとっても多くのメリットをもたらします。
1.従業員のエンゲージメントと生産性の向上
「自分の成長を応援してくれている」と感じた従業員は、企業への信頼感や愛着(エンゲージメント)が高まります。 自らの目標が明確になれば、仕事へのモチベーションが向上し、主体的に取り組むようになります。その結果、組織全体の生産性向上にも繋がります。
2.優秀な人材の定着と採用力の強化
成長のチャンスが多い企業は、それだけで従業員にとって魅力的です。キャリア自律支援は、優秀な人材が「この会社で働き続けたい」という思いを強め、離職防止に効果的です。 さらに、「社員の成長を大切にする企業」という評判は、採用活動においても有利に働き、優秀な人材を引きつける力となります。
3.組織の柔軟性とイノベーションの促進
主体的に学び、新しいスキルを身につける社員が増えれば、会社全体の柔軟性も高まります。
社内外で得た知識や視点が組み合わさることで、これまでにないアイデアやサービスが生まれる可能性も広がります。
従業員のキャリア自律を促す方法
効率的なキャリア自律支援には、制度と文化の両面からアプローチが重要です。
▶関連情報: 全社員のキャリア自律意識の醸成|キャリア開発のパイオニア 日本マンパワー |
1.Will(個人の意思)を尊重した対話の機会
キャリア自律の出発点は、従業員一人ひとりが持つ「Will(どうなりたいか、何をしたいか)」を大切にすることです。とはいえ、上司が期待する成果(Must)を伝えることを軽んじるわけではありません。
重要なのは、一方的に「やらせる」のではなく、本人の価値観や望む働き方、将来の希望に耳を傾けることです。そうした対話を通じて、本人が望む成長の方向性とMustをすり合わせ、両者が重なり合うポイントを見つけていくことが、キャリア自律を支える鍵となります。
上司との1on1ミーティングやキャリア面談などを定期的に実施し、個人の価値観やキャリアプランについて対話する機会を設けることが重要です。そうすることで、メンバーは自分の価値観を意識化できるようになり、日々の業務に自分なりの意味を見出せるようにサポートすることができます。
▶関連記事: 1on1で話すことに困らない!効果的なテーマと具体的な進め方を解説| キャリアコンサルタントLibrary |
▶関連記事: キャリアコンサルタントの活用企業はどのくらい?役割や仕組みの導入メリットも紹介| キャリアコンサルタントLibrary |
2.社内のポストやポジションに関する情報の透明化
「社内にどのような仕事があり、どのようなスキルが求められるのか」という情報が不足していると、従業員は社内でのキャリアパスを描くことができません。
社内公募制度を活性化させたり、各部署の業務内容や必要スキルを積極的に開示したりすることで、情報の透明性を高めることが有効です。これにより、従業員は目標設定をしやすくなります。
3.継続的な学習機会(リスキリング)の提供
従業員が主体的に学ぶためには、企業側からの学習機会の提供が不可欠です。
オンライン学習プラットフォームの導入、資格取得支援制度、外部セミナーへの参加費補助など、多様な学びの選択肢を用意しましょう。 従業員が時代の変化に対応し、市場価値を高め続けられる環境を整えることが、企業の持続的な成長にも繋がります。
4.副業やボランティアなど外部との交流の推奨
副業やNPOでのボランティア活動など、社外での経験は新たなスキルや人脈、広い視野をもたらします。
企業が副業を許可・推奨することは、従業員が社内では得られない経験を積み、自律性を高める上で非常に効果的です。そこで得た知見やスキルが本業に還元され、イノベーションのきっかけとなることも期待できます。
5.キャリア自律を望まない従業員への対応
すべての従業員が積極的にキャリア自律を望むわけではありません。 中には、会社主導で良い、なりゆきに任せたいという従業員もいます。また、求められる変化に強い不安を感じてしまい、身動きが取れないという従業員もいるでしょう。
キャリア自律を一方的に強要することは、かえって能動性を奪うこともあります。まずは組織全体として個々の役割や期待を明確にしつつ、なぜキャリア自律が重要なのかを丁寧に説明し、勇気づけながら、少しずつ意識を醸成していくアプローチが大切です。
キャリア自律の支援に取り組む企業事例
多くの企業が従業員のキャリア自律を支援するために、独自の施策を展開しています。
日清食品ホールディングスの事例
同社では、シニア社員の活躍機会を増やすため、従来49歳までとしていた公募ポストへの挑戦資格の年齢制限を撤廃しました。 年齢に関わらず、意欲のある社員が誰でも新たなチャレンジをできるようにすることで、組織の活性化と個人の成長を促しています。
参考: https://award.atwill.work/stories2019/883/
富士通株式会社の事例
IT企業からDX企業への変革を目指す同社は、2020年からジョブ型雇用を導入しました。 従来の階層別教育を廃止し、社員が自らのキャリアプランに合わせて自由に研修を選択できる学習環境を提供しています。また、社内ポスティング(社内公募)制度を大幅に拡大し、社員が主体的にキャリアを選択できる機会を増やしています。
参考: https://pr.fujitsu.com/jp/news/2022/04/21.html
株式会社丸井グループの事例
同社では「手挙げ文化の醸成」を長年にわたり推進しています。 かつては会社が与える研修が中心でしたが、現在では学びの場への参加をすべて任意の手挙げ制に変更しました。「学びたい」「成長したい」という意欲のある社員に積極的に投資することで、自発的に学ぶ文化を醸成し、現在では85%の社員が何らかの学びに手を挙げるまでになっています。
参考:
https://www.0101maruigroup.co.jp/recruit/newgraduate/career/
参考:
https://pdf.0101maruigroup.co.jp/ir/pdf/i_report/2023/i_report2023_14.pdf
まとめ
キャリア自律は、変化の激しい時代を生き抜くために、個人と企業の双方にとって不可欠な概念です。
個人は主体的に学び、キャリアを築くことで人生の満足度を高めることができ、企業は自律的な従業員を育成・支援することで、持続的な成長と競争力強化を実現できます。
本記事で紹介したポイントを参考に、自律的なキャリア形成への第一歩を踏み出してみましょう。