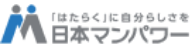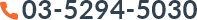キャリアコンサルタントLibrary
人の力になりたいという気持ちが原動力!それが社会の役に立つのがキャリアコンサルタント資格です!!
その他
キャリア・パスポートの目的とは?小中高での連携や家庭でできるサポートを解説
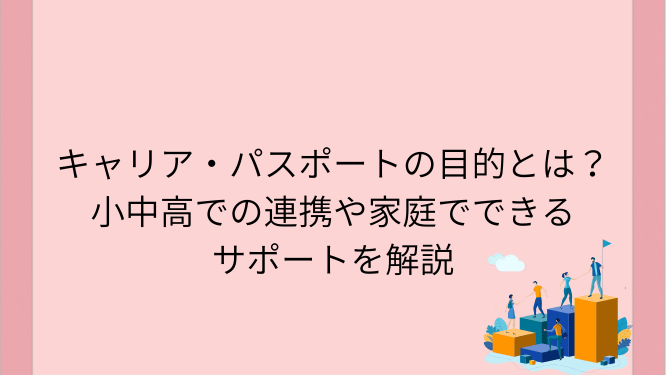
近年、教育現場で「キャリア・パスポート」という言葉を耳にする機会が増えたのではないでしょうか。2020年度から全国の小・中・高等学校で導入されたこの取り組みは、子どもたちの未来を切り拓く力を育むための重要なツールと位置づけられています。しかし、その具体的な内容や目的、活用方法について、まだよく知らないという方も少なくないでしょう。
この記事では、キャリア・パスポートの基本的な概要から、その目的、具体的な進め方、さらには学校や家庭でどのように活用できるかまで、分かりやすく解説します。
キャリア・パスポートとは?
キャリア・パスポートは、文部科学省が推進している取り組みで、小学校から高等学校までの学校生活を通じて、児童生徒が学習活動や学校内外での多様な経験を記録・蓄積し、振り返ることで自己理解を深め、将来の生き方やキャリア形成を考えるために活用する教材です。2020年度から始まったキャリア教育の中核
キャリア・パスポートは、2020年度から順次施行された新しい学習指導要領に伴い、全国の小学校、中学校、高等学校で導入されました。これまでも各学校で「キャリアノート」などの名称で同様の取り組みは行われていましたが、小・中・高と学校段階を超えて活用し、学びを繋いでいく点が大きな特徴です。目的は「生きる力」を育むこと
キャリア・パスポートの最大の目的は、変化の激しい社会をたくましく生き抜くために必要な「生きる力」を育むことです。急速に変化する社会の中で、子どもたちが主体的に自らの人生を切り拓いていくためには、従来のような知識の習得だけでなく、多様な価値観を持つ人々と協働し、新たな価値を創造していく「生きる力」が求められます。 キャリア・パスポートは、生徒自らが学びや活動の記録を付け、それを振り返ることで、自分自身の成長を実感し、次の目標設定や将来の生き方を主体的に考える力を養うことを目指しています。ポートフォリオとの違い
キャリア・パスポートは、生徒が自身の学びのプロセスや成果を記録・蓄積していく「ポートフォリオ」の一種です。一般的なポートフォリオが作品集や学習成果の記録であるのに対し、キャリア・パスポートは、学習活動だけでなく、学校行事、部活動、地域活動、家庭での取り組みなど、より幅広い活動を対象とし、自己の成長やキャリア形成に焦点を当てている点が特徴です。| 項目 | キャリア・パスポート | 一般的な学習ポートフォリオ |
|---|---|---|
| 目的 | 自己理解、キャリア形成、生きる力の育成 | 学習成果の評価、学習プロセスの可視化 |
| 記録内容 | 教科学習、学校行事、部活動、地域活動など | 主に教科学習の成果物(レポート、作品など) |
| 活用期間 | 小学校から高等学校までの12年間 | 単年度や特定の期間 |
| 焦点 | 自己の成長、将来の生き方 | 学習内容の達成度 |
キャリア・パスポートで育む4つの能力
文部科学省は、キャリア教育を通じて育成すべき能力として、以下の4つの基礎的・汎用的能力を挙げています。キャリア・パスポートは、これらの能力をバランスよく育むためのツールです。人間関係形成・社会形成能力
他者の個性や考えを理解し、尊重しながら、自分の意見を適切に表現し、協力して社会に貢献する力です。グループ活動や学校行事などの記録を通じて、他者との関わり方を振り返り、コミュニケーション能力を高めます。自己理解・自己管理能力
自身の興味・関心や価値観を理解し、目標に向かって粘り強く取り組む力です。定期的に活動を記録し振り返ることで、自分の長所や課題を客観的に把握し、自己肯定感を育みます。課題対応能力
身の回りの課題を発見し、解決に向けて他者と協力しながら主体的に行動する力です。探究学習やボランティア活動などの経験を記録することで、課題解決のプロセスを学びます。キャリアプランニング能力
学ぶことや働くことの意義を理解し、多様な生き方の中から自分の役割や目標を考え、将来を設計していく力です。自身の成長記録を時系列で振り返ることで、将来の夢や目標を具体的に描く手助けとなります。キャリア・パスポートの進め方とポイント
キャリア・パスポートを効果的に活用するためには、いくつかの重要なポイントがあります。小学校・中学校・高等学校での一貫した活用
キャリア・パスポートは、小学校入学から高等学校卒業までの12年間、継続して記録・活用されることを前提としています。学校が変わる際には、生徒自身がこれまでの記録を持参し、次の学校へと引き継がれます。 この一貫した記録により、生徒は長期的な視点で自身の成長を振り返ることができます。学校生活全体を記録する3つの視点
記録する内容は、特定の教科の学習だけに偏らないように注意が必要です。文部科学省は、以下の3つの視点をバランスよく含めることを推奨しています。| 視点 | 具体例 |
|---|---|
| 教科学習 | 各教科での学び、探究活動、発表など |
| 教科外活動 | 学校行事、委員会活動、部活動、係活動など |
| 学校外の活動 | ボランティア、地域活動、家庭での役割、習い事など |