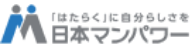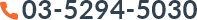キャリアコンサルタントLibrary
人の力になりたいという気持ちが原動力!それが社会の役に立つのがキャリアコンサルタント資格です!!
事例紹介 その他
人材育成の課題とは?原因と解決策を具体例で解説
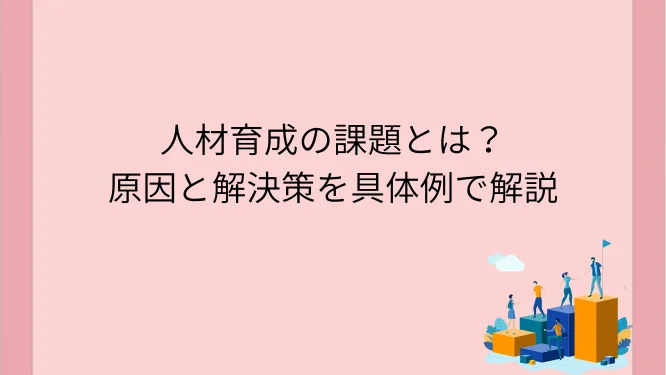
人材育成でよくある9つの課題
多くの企業が人材育成の重要性を認識しつつも、さまざまな課題に直面しています。ここでは、企業が抱えがちな9つの代表的な課題について解説します。自社の状況と照らし合わせながら、課題を特定するための参考にしてください。課題1:育成のための時間やリソースが不足している
育成対象者も、日々の業務に追われているのが実情です。厚生労働省の調査によれば、人材育成の問題点として「指導する人材が不足している」と回答した企業は58.5%、「人材育成を行う時間がない」は45.3%にものぼります。 育成のための時間を確保できなければ、計画的な指導は困難になるでしょう。また、研修費用や外部サービスの導入といった金銭的なコストも、企業にとっては大きな負担となる場合があります。
【参考】 https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/001132160.pdf
課題2:指導者側のスキルや意識が不足している
部下や後輩を育成する立場にある管理職や先輩社員が、必ずしも指導のプロフェッショナルであるとは限りません。なぜなら、自身の業務で成果を出すことと、他者を育成することは全く異なるスキルが求められるためです。指導方法がわからなかったり、育成に対する意識が低かったりすると、効果的な人材育成は期待できません。その結果、育成が形骸化し、部下や後輩の成長機会を奪ってしまうことになります。課題3:育成しても社員がすぐに辞めてしまう
時間とコストをかけて育成した人材が、スキルを習得したタイミングで離職してしまうのは、企業にとって大きな損失です。 この問題の背景には、育成後のキャリアパスが不明確であったり、成長や成果が評価・処遇に適切に反映されなかったりするケースが多く見られます。 社員が「この会社で働き続けても成長できない」と感じてしまうことが、離職の大きな引き金となります。課題4:育成計画が場当たり的になっている
明確な育成方針や計画がないまま、目の前の問題に対応するだけの場当たり的な研修を行っているケースも少なくありません。「とりあえず新入社員研修だけは実施している」という企業も多いのではないでしょうか。しかし、どのような人材を育てたいのかというゴールが不明確なままでは、育成施策に一貫性がなく、効果も限定的になってしまいます。課題5:社員の学習意欲を引き出せない
企業がどれだけ充実した研修プログラムを用意しても、受講する社員本人に学習意欲がなければ、その効果は半減してしまいます。 「研修は業務の一環で仕方なく受けている」という意識では、知識やスキルは身につきにくいでしょう。社員の意欲が低い背景には、研修内容が実務とかけ離れていたり、キャリアアップに繋がるイメージが持てなかったりすることが考えられます。研修内容が今後の業務やキャリアにどのようにつながるのかということを明確にする必要があります。課題6:育成の効果が実感・測定できない
多くの時間やコストを投じて人材育成を行っても、その効果が目に見えにくいという課題があります。 研修前後で社員の行動や成果がどう変わったのかを具体的に測定できていない企業は少なくありません。効果が不明確なままでは、育成施策の改善や、新たな投資への経営判断も難しくなり、結果として人材育成への取り組みが停滞する悪循環に陥ります。課題7:経営層の理解や協力が得られない
人材育成は、すぐに利益に結びつくものではないため、経営層からその重要性を十分に理解されず、必要なリソースを割いてもらえないことがあります。 人事部門がどれだけ素晴らしい育成プランを立てても、経営層の協力がなければ全社的な取り組みとして推進することは困難です。現場からも「忙しいのに研修ばかり受けさせる」といった反発を招きかねません。人材育成を有益なものとするためには、経営層や現場の協力・理解が不可欠です。課題8:スキルや技術の変化が速く追いつけない
現代は、デジタルトランスフォーメーション(DX)やAIの進展など、ビジネス環境が目まぐるしく変化する時代です。次々と新しいスキルや知識が求められるため、企業の人材育成がそのスピードに追いつけないという課題も深刻化しています。一度構築した研修プログラムも、すぐに陳腐化してしまう可能性があります。研修プログラムは時代の変化に合わせて、 絶えず適切な内容かどうかを精査する必要があります。課題9:個人のキャリアプランと会社の方向性が合わない
終身雇用が当たり前ではなくなった現代において、社員一人ひとりが自身のキャリアプランを考えるようになっています。企業が示す成長の方向性と、社員個人が描くキャリアプランが一致していない場合、社員は成長意欲を失い、エンゲージメントの低下や離職に繋がります。企業は、社員のキャリア自律を支援する視点を持つことが重要です。なぜ人材育成の課題は生まれるのか?主な原因を解説
前述したような課題は、なぜ発生するのでしょうか。その背景には、企業組織に根差した構造的な原因が存在します。ここでは、代表的な3つの原因について解説します。原因1:明確な人材育成ビジョンが欠如している
最も根本的な原因は、企業として「どのような人材を、何のために育てるのか」というビジョンや戦略が明確になっていないことです。経営戦略と連動した人材育成ビジョンがなければ、育成施策は場当たり的で一貫性のないものになります。まずは、自社の目指す姿から逆算して、必要な人材像を定義することがすべての出発点となります。原因2:現場任せで組織的なサポート体制がない
日本の企業では、OJT(On-the-Job Training)が人材育成の中心になることが多いですが、その実態は指導役の先輩や上司に丸投げされているケースが少なくありません。人事部と現場が連携し、指導者をサポートする仕組みや、業務を代替する体制がなければ、指導者の負担が増大し、育成の質も低下してしまいます。 組織全体で人材を育てるという文化の醸成が不可欠です。原因3:評価制度と育成が連動していない
人材育成と人事評価制度が連動していないことも、大きな原因の一つです。例えば、研修で新しいスキルを習得し、業務の成果を上げても、それが昇給や昇格に結びつかなければ、社員の学習意欲は高まりません。 同様に、部下を育成することが管理職の評価項目に含まれていなければ、管理職は自身の業務を優先し、部下育成に本腰を入れないでしょう。育成への取り組みや成長が、正当に評価される仕組みを構築することが重要です。人材育成の課題を解決するための5つのステップ
人材育成の課題を克服し、効果的な育成を実現するためには、計画的かつ体系的なアプローチが求められます。ここでは、課題解決に向けた具体的な5つのステップを紹介します。ステップ1:現状の課題と理想の状態を明確にする
まずは、自社が抱える人材育成の課題を具体的に洗い出すことから始めます。社員アンケートや管理職へのヒアリング、スキルマップの作成などを通じて、現状を客観的に把握しましょう。その上で、「3年後には、社員の半数がDX関連の資格を保有している」「次世代のリーダー候補が5名育っている」といった、理想の状態(ゴール)を具体的に設定します。ステップ2:育成の目標と育成計画を策定する
理想の状態を実現するために、階層別(新入社員、中堅社員、管理職など)や職種別に、具体的な育成目標を設定します。その目標を達成するための育成計画を、期間や手法、予算なども含めて策定します。この際、企業の経営戦略と連動していること、そして現実的に実行可能な計画であることが重要です。ステップ3:多様な育成手法を組み合わせて実施する
人材育成の手法は一つではありません。OJTやOff-JT(集合研修)はもちろん、eラーニング、メンター制度、1on1ミーティング、ジョブローテーションなど、多様な手法が存在します。 育成目標や対象者に合わせて、これらの手法を効果的に組み合わせることが成功のカギです。例えば、知識のインプットはeラーニングで行い、実践的なスキルはOJTで習得するといった使い分けが考えられます。
| 育成手法 | 特徴 |
|---|---|
| OJT | 実務を通じて、実践的なスキルやノウハウを習得できる。指導者の負担が大きい。 |
| Off-JT(集合研修) | 体系的な知識を一度に多くの社員に教えることができる。現場の業務から離れる必要がある。 |
| eラーニング | 時間や場所を選ばずに学習できる。個人の進捗管理が容易。 |
| メンター制度 | 年次の近い先輩が新人の悩み相談に乗り、精神的なサポートを行う。早期離職防止に効果的。 |
| 1on1ミーティング | 上司と部下が定期的に対話し、成長の振り返りやキャリア面談を行う。エンゲージメント向上に繋がる。 |
ステップ4:育成の効果を測定しフィードバックを行う
育成計画は実行して終わりではありません。定期的にその効果を測定し、評価することが重要です。 研修後の理解度テストやアンケート、行動変容の観察、業績への貢献度など、多角的な視点で効果を測ります。測定結果は、育成対象者本人や指導者にフィードバックし、次の成長に繋げるとともに、育成計画自体の改善にも役立てることができます。
| 育成施策 | 効果測定の指標例 |
| 新入社員研修 | 配属後の定着率、上司や先輩からの評価、一人で業務を遂行できるまでの期間 |
| スキル研修 | 資格取得率、特定業務の生産性向上率、エラー発生率の低下 |
| 管理職研修 | 部下のエンゲージメントスコア、担当部門の目標達成率、部下の離職率の低下 |
ステップ5:継続的に計画を見直し改善する
ビジネス環境の変化や、社内の状況に応じて、人材育成計画は常に見直しが必要です。一度作成した計画に固執するのではなく、PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を回しながら、継続的に改善していく姿勢が求められます。定期的に計画の進捗を確認し、より効果的な育成方法を模索し続けることが、企業の持続的な成長を支えます。【階層別】人材育成のポイント
全ての社員に同じ育成を行うのではなく、それぞれの階層が抱える課題や役割に応じて、育成のポイントを変えることが重要です。新入社員:社会人基礎力と早期離職の防止
新入社員に対しては、ビジネスマナーや基本的なPCスキルといった社会人としての基礎力を身につけさせることが最優先です。同時に、慣れない環境からくる不安を解消し、早期離職を防ぐための精神的なサポートも欠かせません。 相談しやすい先輩社員をメンターとしてつけるメンター制度の導入などが有効です。中堅社員:専門性とリーダーシップの育成
中堅社員は、現場の中核として実務をこなしながら、将来的にはリーダーとしての役割も期待される層です。自身の専門性をさらに深めるためのスキルアップと同時に、後輩指導やチームマネジメントの基礎となるリーダーシップ開発の機会を提供することが重要です。管理職:部下育成スキルと組織マネジメント能力の向上
管理職には、プレイングマネージャーとして自身の業績を上げることだけでなく、部下を育成し、チーム全体の成果を最大化する役割が求められます。コーチングやフィードバックのスキルを学ぶ研修や、組織のビジョンを部下に浸透させるためのマネジメント研修などが効果的です。人材育成の課題解決に成功した企業事例
ここでは、実際に人材育成の課題解決に取り組んだ企業の事例を紹介します。資生堂の変革リーダー育成
資生堂は「PEOPLE FIRST」の理念のもと、グローバル共通の人材像「TRUST 8コンピテンシー」を策定し、2023年に銀座にShiseido Future Universityを開設しました。選抜型研修を中心としたリーダーシップ開発プログラムや、女性リーダー育成塾「NEXT LEADERSHIP SESSION for WOMEN」を実施した結果、日本国内の女性管理職比率が2017年の29%から2025年には41.1%へと大幅に向上したことが同社公式サイトで報告されています。グローバル共通の評価基準の導入により、客観的な人材評価と処遇の実現も達成しています。
参考URL: https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/labor/training.html
トヨタの現場主義による人材育成
トヨタは「モノづくりは人づくり」の理念に基づき、OJT(On the Job Training)を人材育成の基本に据えています。特に優秀で意欲の高い従業員に対しては、将来のリーダー候補として中長期的・計画的な育成を実施し、業務経験を通じた育成目的のローテーションを行っています。上司が部下に問題解決の分析手法や対策の方向性を伝授する日々のOJTの繰り返しにより、組織全体のパフォーマンス向上を実現していることが同社公式サイトで詳述されています。
まとめ:戦略的な人材育成で企業の未来を創る
本記事では、人材育成における9つの課題と、その解決に向けた5つのステップについて解説しました。人材育成の課題は、時間やコストの不足といった表面的な問題だけでなく、企業のビジョンや評価制度とも深く関わっています。 まずは自社の課題を正しく認識し、経営戦略と連動した育成計画を立てることが重要です。そして、計画を実行し、効果を測定しながら継続的に改善していくことで、社員と企業が共に成長する好循環を生み出すことができます。この記事が、貴社の人材育成を前に進めるための一助となれば幸いです。 社員の学びやリスキリングなど、キャリア自律をしっかりと丁寧にサポートする専門家を育成することをお勧めします。
関連リンク▶ キャリアコンサルタント養成講座 無料説明会予約はこちら